こんなお悩みありませんか?
この記事で紹介する『文章を作る3つの心構え』を実践すると、ライティング初心者でもプロ並みの文章を書くことが可能です。
なぜなら、僕も実際に実践して、未経験から半年でフリーランスとして活動できるようになったためです。
今回は記事作成の際の心構え3つを含めた、書き方のコツを15個に分けて解説するので、できるところから1つずつ実践してみてください!
実際に書いていく際や書いた記事をチェックするときには、この記事を「いい文章かどうかのチェックリスト」としても活用してみてください。
【初心者必見】ライティングの全体像
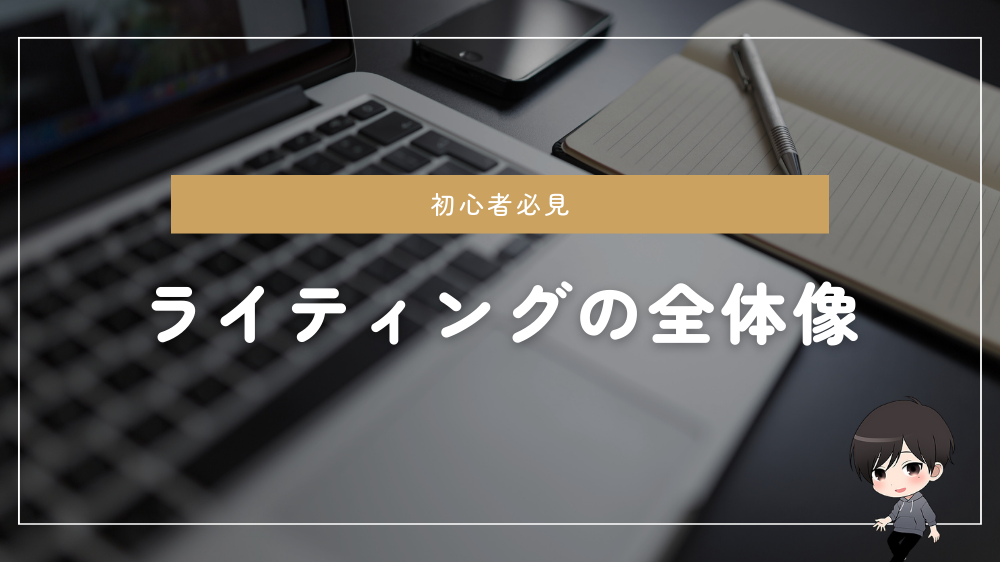
記事作成の際には「書き出し・本文・まとめ」の3つに分けられます。
【h1】タイトル
▶︎書き出し(読者を本文に引き込む)
【h2】見出し
▶︎本文
【h2】見出し
▶︎本文
【h2】見出し
▶︎本文
(記事で伝えたいことを書く)
(最後まで読者を引き込む工夫)
【h2】まとめ
▶︎読者を誘導する文章
↓
CTA(次にとってほしい行動へ誘導)
それぞれ役割が異なるため、書き方も違います。
まずは「文章を書く前の準備や心構え」の紹介です。
文章を書く前の準備・心構え3つ
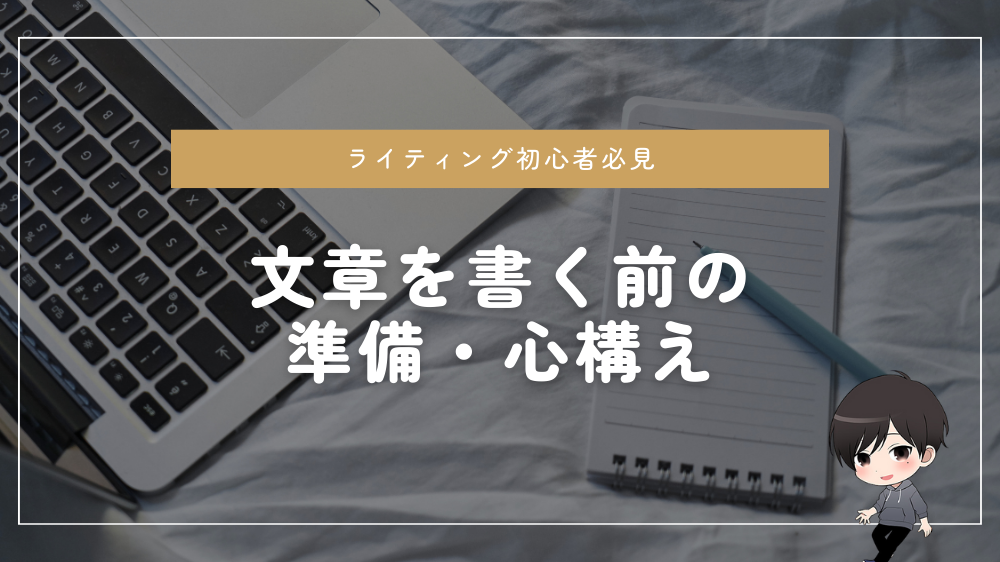
事前に、
「記事では何を書きたいのか」
「どんな文章が必要なのか」
「どんな文章構成だと読みやすいのか」
を理解し、準備した上で書き進めないと、支離滅裂な文章ができあがります。
次の3つを理解するのとしないのとでは文章の質が大きく変わるので、じっくり読み進めてください。
- ストレスのない文章を書く
- 記事構成を決める
- 論理的な文章構成を使う
ひとつずつ解説していきます。
❶ストレスのない文章を書く

ここであなたに1つ質問です。
Q.GoogleやSNSで、たまたま見かけた記事が「読みにくい文章」だったらどうしますか?
基本的には、すぐにそのページを閉じると思います。
多くの人は「たまたま時間があるときに見かけた」程度の動機で読み進めるため、基本的に記事を読むモチベーションは高くありません。
だからこそ、読者にストレスを与えない読みやすい文章を書く必要があります。
❷記事構成を決める
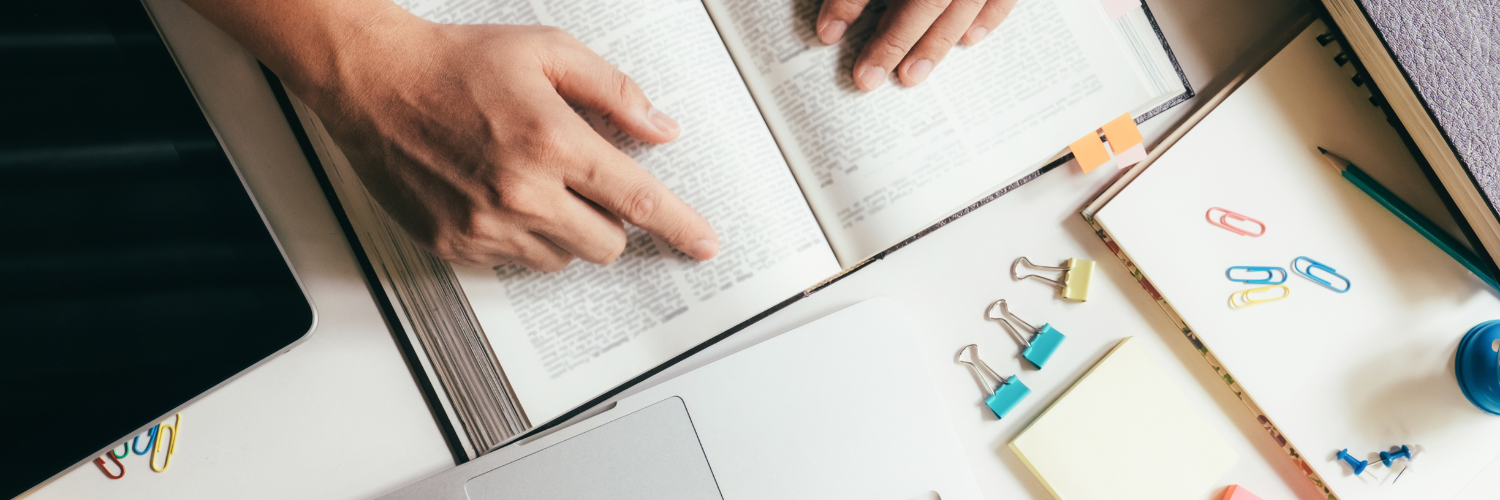
文章を書く前に「記事構成」は必ず準備しましょう。
なぜなら、記事構成を作っておくと、記事の全体像を把握できるためです。
たとえば、以下のようなポイントに気づけます。
・記事全体の流れはわかりやすいか
・最初の「書き出し」は変ではないか
・最後の「まとめ」は締まりがあるか
・情報が重複していないか
もちろん、構成を作るのには時間がかかります。
しかし「構成なしで発生する恐れのある手戻り作業」を考えると、むしろ構成を作るほうが時間の節約につながります。
文章を書くのが苦手な人ほど、構成は作り込んでおきましょう。
構成の書き方については以下の記事を参考にしてください。
参考記事:【人気ブログの作り方】初心者でもできる記事構成の作り方:3ステップ
❸論理的な文章構成を使おう

記事を書く際は、論理的な文章構成を心がけましょう。
代表的な文章構成として「PREP法」がおすすめです。
【参考】
PREP法とは「結論→理由→具体例→結論」の順番で構成された文章のこと。
プレゼンやビジネス文書で使われる手法で、多くのブログ記事でも活用されています。
文章に説得力が生まれ、短時間で相手に内容を伝えられ、かつ誰でも使いやすいのが特徴です。
【具体例】
- 結論:文章構成にはPREP法がおすすめです。
- 理由:なぜなら内容が伝わりやすいからです。
- 具体例:例えば、プレゼンやビジネス文書などでも使われています。
- 再結論:だからブログ初心者にもPREP法がおすすめです。
例の通り、
「結論→理由→具体例→再結論」の文章構成になっています。
もちろん、すべての文章をPREP法で書く必要はなく、流れによっては理由や具体例を省略してもかまいません。
とはいえ、PREP法を使えば論理的な文章構成で記事を書き進められるので、ブログの始めたては積極的に活用しましょう。
以上が「文章を書く前の準備・心構え」でした。
上記を踏まえて、以下で紹介するコツを実践してみてください。
【ライティング初心者必見】文章の書き方の6つのコツ

0から記事を書く際に、はじめからコツのすべてを実践しようとすると、心が折れてしまうと思います。
まずは、次の6つのコツから取り組んでみましょう。
- 同じ接続詞は避ける
- 同じ文末は避ける
- 無駄な単語や装飾は削除する
- 遠回しな表現は避ける
- 漢字・ひらがな・数字のバランス見る
- 一度読んで誤字脱字をチェックする
これらだけでも意識して記事を書くと、論理的な文章に仕上がります。
上から順に優先度が高いので、じっくり読み込んでください。
❶同じ接続詞は避ける
機械的な印象や読んでいて違和感を与えてしまうので、同じ接続詞を連続して使うのは避けましょう。
連続使用を避けるには、接続詞のバリエーションを増やす必要があります。
以下では、PREP法で使える接続詞を紹介するので参考にしてください。
【理由】
なぜなら、その根拠は、そのわけは、理由は、〜だから
【具体例】
例えば、具体的には、例としては、どういうことかと言うと
【再結論】
そのため、つまり、したがって、以上の理由で、このように
接続詞のバリエーションが増えてきたら、見出し内で同じ接続詞は使わないよう意識してみてください。
さらに「1度使用した接続詞は2つ先の見出しまで使わない」ようにすると、より違和感の少ない文章を作ることができます。
❷同じ文末は避ける
同じ文末の使用を避ければ、人間味がある文章に仕上がります。
とはいえ、文章ごとに文末を変えることが厳しい場合もあります。
そのため、基本的には同じ文末が3回連続しないように意識すれば大丈夫です。
以下に、文末の例をまとめます。
です・ます・ですよ・~しますね・~ですよね・~しましょう・~してください
❸無駄な単語や装飾は削除する
以下5つの言葉を削ると文章がすっきりするので、参考にしてみてください。
接続詞を削る
×→彼はとても賢い。しかも誰にでも優しい。
◯→彼はとても賢く、誰にでも優しい。
文章が滑らかに連結されていれば、接続詞は削除しても問題ありません。
「どうしても必要なら接続詞を使う」程度の意識でいいと思います。
理由は、接続詞を多用するとまわりくどい印象になるからです。
「という」を削る
×→B’zというモンスターバンドは、僕の人生に大きな影響を与えたロックユニットです。
◯→B’zは、僕の人生に大きな影響を与えたモンスターバンドです。
内容説明を表す「という」は、削除してもほとんど影響がありません。
多用しやすく冗長な表現になっていることが多いため、積極的に削除しましょう。
代名詞を削る
×→新企画で事件がおきました。その企画の中で予想外のトラブルが起こり、その影響を受けました。
◯→新企画で事件がおきました。企画の中で予想外のトラブルが起こり、影響を受けました。
代名詞はなくても意味が通るので、削除してスッキリさせましょう。
修飾語を削る
×→とても大きな流れ星が見えて、子どもたちの気分はテンションMAXで最高潮になった。
◯→大きな流れ星が見えて、子どもたちの気分は最高潮になった。
同じ意味の修飾語が重なっている場合、削除すると読みやすくなります。
❹遠回しな表現は避けよう
まず結論を書きましょう。
読者は一番に「答え」を求めているので、最初に結論(答え)を伝えると満足度が上がります。
意図的に遠回しの表現を入れるケースもありますが、ブログ初心者にとっては高等テクニックなのであまりおすすめしません。
❺漢字・ひらがな・数字のバランスを見よう
漢字とひらがなのバランスを調整しながら、文章のビジュアルに意識を向けてみましょう。
漢字ばかりの文章だと読者に難しいイメージを与え、読まれずに離脱されやすくなります。
一方で漢字が少ないと、拙く中身のない文章に思われ「読むまでもない」と判断されるかもしれません。
そのため、読み直す際に漢字とひらがなの量を調整し、パッと見た時の印象をよくするようにしてください。
❻一度読んで誤字脱字をチェックしよう
一度、ここまでで紹介した「1~5のコツ」を意識して文章を書ききってみてください。
ここまでのコツだけでも意識して記事を書けば、60%~70%の土台ができたのも同然です。
文章が書けたら、誤字脱字のチェックをしましょう。
誤字脱字がある記事には、以下のようなデメリットがあります。
・読者のストレスになる
・事実誤認につながる
・記事全体の信頼性をなくす
上記のようなデメリットを避けるため、下記のような誤字脱字の起きやすいポイントを中心に文章をチェックしましょう。
・数字:打ち間違いや事実誤認がないか
・同音異義語:変換ミスがないか
・固有名詞:手打ちではなくコピペ
さらに魅力的な文章を作る9つのコツ
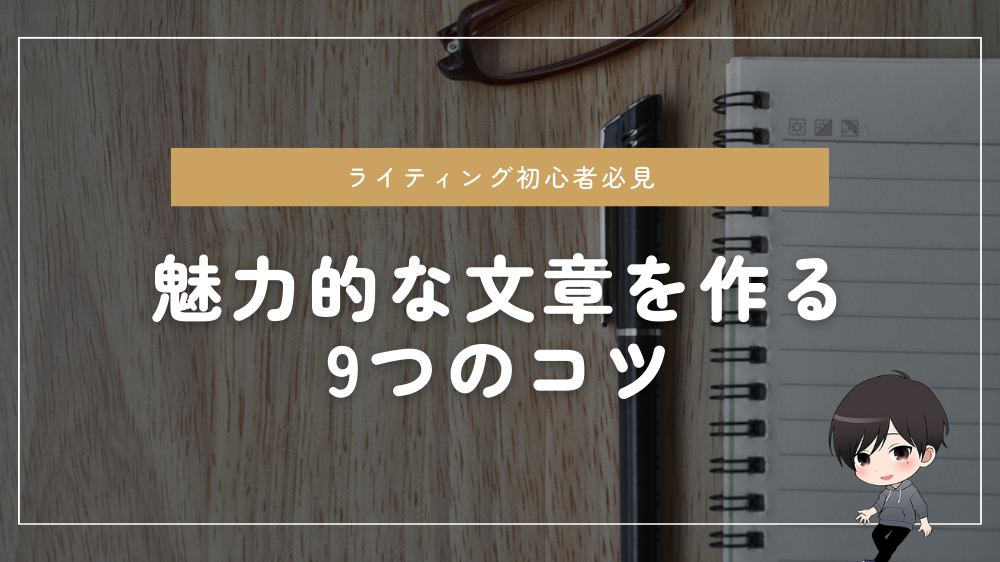
ここまででのコツを活用して一度書き上げた「後」は、さらに魅力的な文章にブラッシュアップしていきましょう!
【魅力的な文章を作る9つのコツ】
- 装飾を使う
- 積極的に画像を使う
- 吹き出しを活用する
- 難しい文章や単語を入れ替える
- 数字を使う
- 「こと」はできるだけ削除する
- 「の」「と」「や」連続使用は避ける
- 「こそあど」は避ける
- 係り受けの距離を近づける
これから紹介する9つのコツを実践すれば、論理的な「読みやすい文章」に仕上がります!
❶装飾を使う
記事の途中、ポイントごとに囲い線や背景色を変更させる装飾を施しましょう。
装飾を施すことで次の2つの効果があります。
- 読者に文章を飽きさせない
- 読者が理解しやすくする
❷積極的に画像を使う
画像化できる箇所は、積極的に画像にしましょう。
文章のほうがわかりやすいケースもありますが、画像を入れると記事全体の雰囲気が変わります。
単調な印象ではなくなるため、画像の使用はおすすめです。
❸吹き出しを活用する
「リアルさ」を強調できたり、メリハリをつけられたりするため、ピンポイントで吹き出しを活用しましょう。
吹き出しとは、実際に人やキャラクターがしゃべっているように見せられる装飾です。
読者がブログ記事を読むテンポを調整でき、箸休め的な効果も期待できます。
❹難しい文章や単語を入れ替える
難しい文章や単語は読者のストレスになるので、しっかり見直しましょう。
少なくとも、以下3つのポイントはチェックしてください。
①難しい単語は簡単な言葉に変換
彼は眉目秀麗だ → 彼は顔立ちが整っていてとても美しい②難しい言い回しは簡単な言葉に変換
彼は顔立ちが整っていてとても美しい → 彼はとてもかっこよかったので憧れの的だった③抽象的な言葉を具体的にする
彼女はとても可愛くて輝いていた → 彼女は有村架純似で多くの人の注目を集めた
❺数字を使う
数字を使うと、文章の内容が具体的になって読者の興味をひきやすいです。
以下のとおり、数字を入れられる部分にはできるだけ数字を記載しましょう。
【数字を入れられる箇所】
・日付
・経過時間や日数
・金額(収益額など)
・大きさ
・広さ
❻「こと」はできるだけ削除する
「◯◯すること」と名詞化する「こと」はできるだけ削除しましょう。
文章のまわりくどさがなくなります。
❼「の」「と」「や」の連続使用は避ける
「の」の事例
×
僕の名前の由来は歌舞伎役者の中村團十郎さんにあります。◯
僕の名前は、歌舞伎役者中村團十郎さんに由来します。
「や」の事例
×
さるやキジや犬や猫が彼女のお気に入りみたいだ◯
さるやキジ、犬、猫が彼女のお気に入りみたいだ
「の」を連続使用すると、拙さがでるので避けましょう。
また「と」や「や」を連続させると読みにくいので、先頭だけ「や」を使ったらあとは「、」でつなぐとわかりやくなります。
(「◯や◯、◯、◯」または「◯と◯、◯、◯」)
❽「こそあど」は避けよう
×
これは、あの人が、それを使用して、どうかしたらしい。◯
この時計は、佐藤さんがハンマーを使用して、壊したらしい。
「これ」「あの」「それ」「どう」といった指示語は、できる限り最小限にしましょう。
指示語の内容を判断する必要があるため読み手の手間になり、かつ文章の意味が曖昧になるからです。
❾係り受けの距離を近づけよう
×
とてもかっこいい三浦さんの息子がいます。◯
三浦さんの息子はとてもかっこいいです。
係り受けの言葉には「主語と述語」と「修飾語と被修飾語」があります。
係り受けの距離を近づけるように心がけましょう。
読みやすくなるだけでなく、読み間違いを防げるからです。
【ライティング初心者必見】文章の書き方まとめ

今回は、記事のなかでも本文の書き方に特化して解説しました。
紹介したコツを意識して取り組めば、文章の質も高まって読みやすくなるはずです!
とはいえ、いきなりすべてのコツを活用するのは難しいので、まずは「PREP法」だけでも意識しましょう。
- 結論:主張したいこと
- 理由:なぜその主張をしたいのか
- 具体例:理由を補強する事例
- 再結論:もう一度結論を伝える
PREP法で記事を書ければ、それだけで論理的な文章に仕上がり、執筆スピードもアップします。
慣れたら、6個のコツを意識して文章に磨きをかけていきましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。
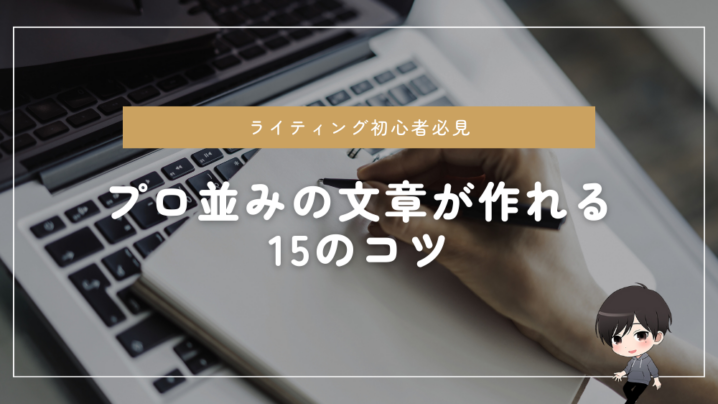
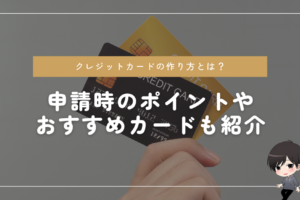
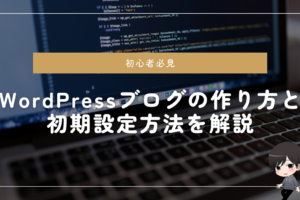
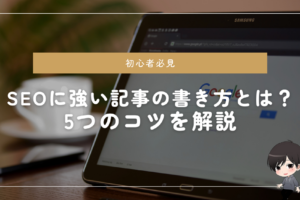


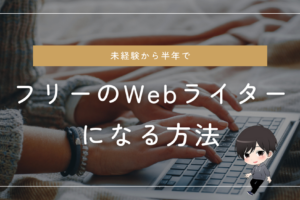
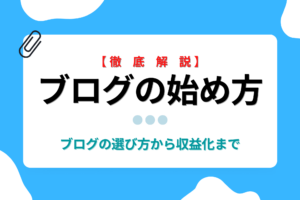

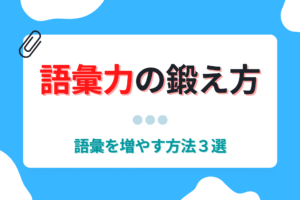
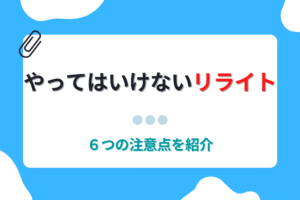
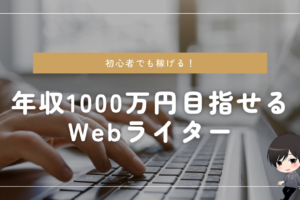


コメントを残す